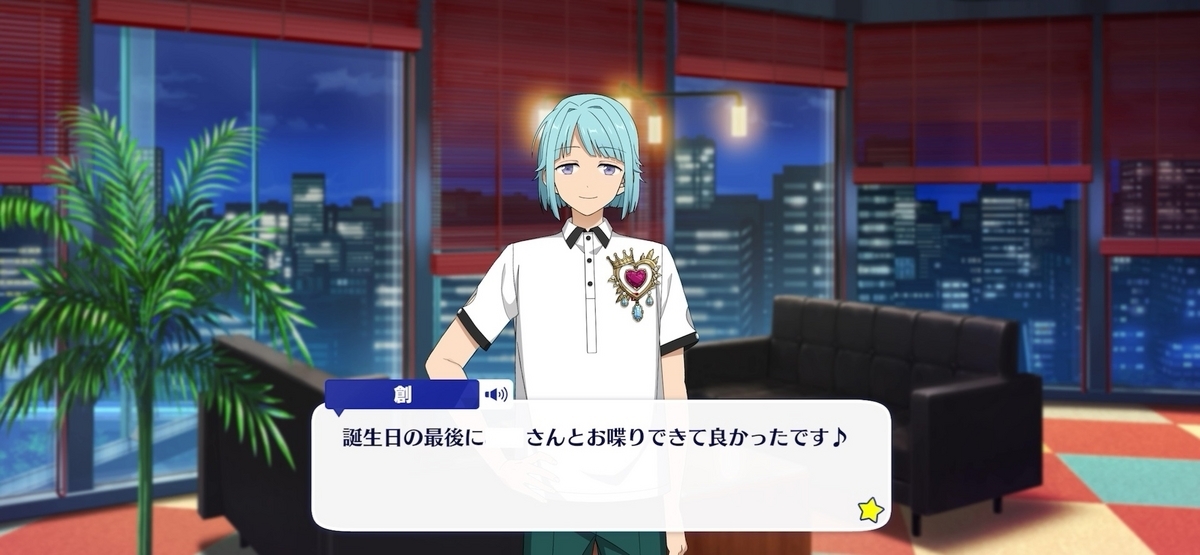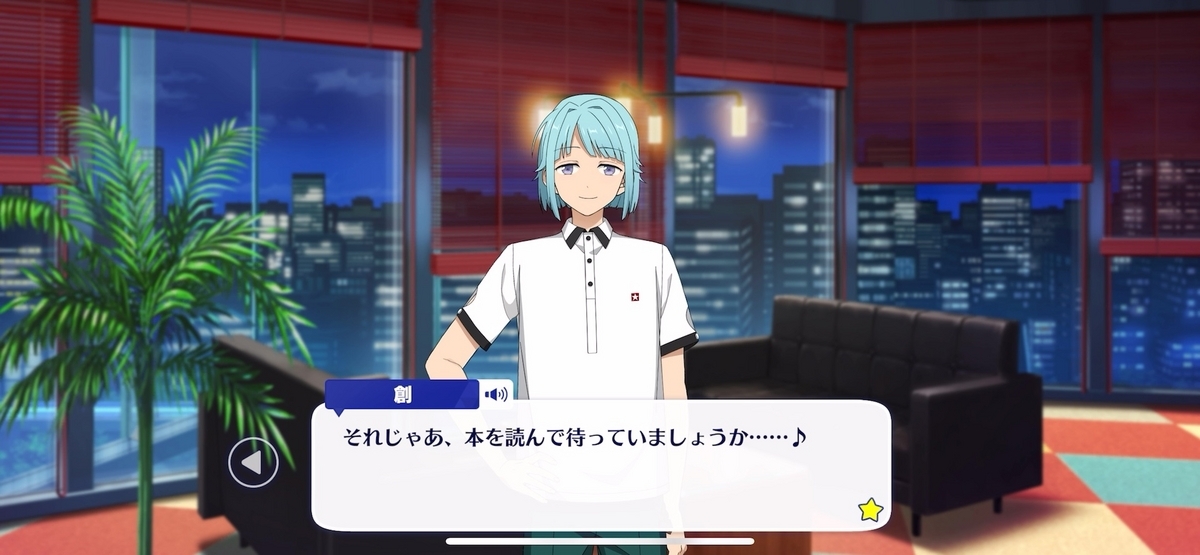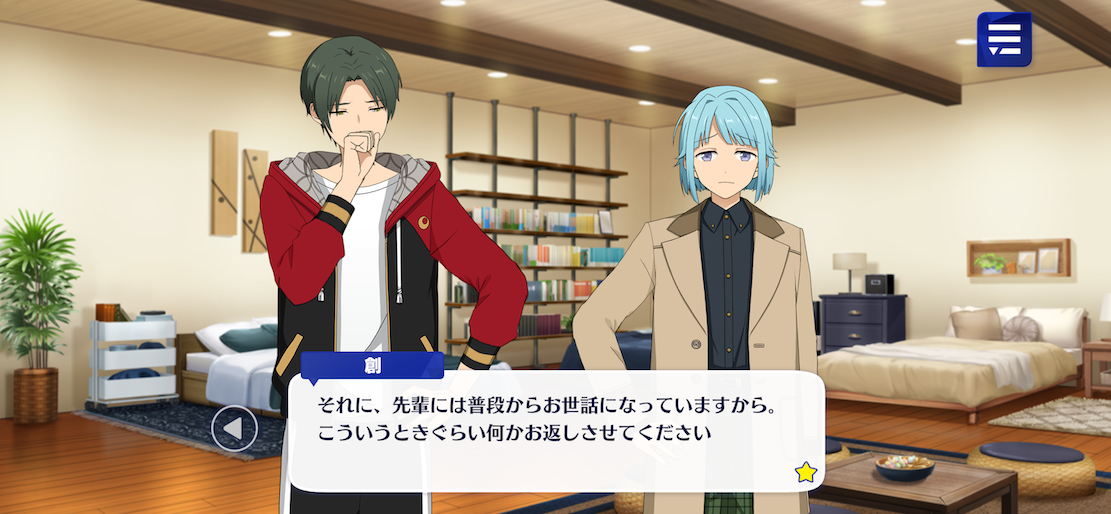Ra*bitsのアルバム『TRIP』*1の簡単な感想です。特に、創くんにフォーカスして。
ひとまず第一印象で感じたことや考えたことを中心に。本当はもっと時間をかけて考えたいところもたくさんありますが。
当ページは、Happy Elements株式会社「あんさんぶるスターズ!!」の画像を利用しております。該当画像の転載・配布等は禁止しております。©Happy Elements K.K
もくじ
アルバムジャケットイラスト
空の旅、「宙」の旅
「TRIP」ということで、「Ra*bits」は空の旅なのでしょうか。「空」というより、「宙」(宇宙)かもしれませんが。飛行機というより、スペースシャトルのような。

航空チケットっぽいデザインや、MVのステージ(「ヒカリスペクトル」で使われていますが、アプリ内キャンペーンによると「単独ライブ」のステージだとわかる)などは、空港のバゲッジクレームっぽい感じもある(あの回転寿司みたいなやつね)。アルバムのオープニングとなる「ヒカリスペクトル」も空に浮かぶ光の輝きを歌っているように思える(後述)。

でもあちこちに星があしらわれた衣装とか、そのステージのデザインにはけっこう「宇宙」っぽさもありますね。「ヒカリスペクトル」MVでも、星がキラキラ輝いたりしていて、ギャラクティック?な感じもある。
Ra*bits衣装で珍しい感じがするビビッドなオレンジ色はアルバムシリーズのテーマ的な色なのかもしれませんが、宇宙服もオレンジ色のイメージがあります。両足のタプっとしたふわふわのレッグウォーマー風アイテムなども、全体のシルエットがスペースシャトルっぽい気もする。かわいい濃紺タイツも、模様をよく見ると、どうやら銀河っぽい。(そういえばこういう夜空や星座のギャラクシーな模様のタイツはどこかに私も持っていました。ロリィタブランドのタイツなどでこういうのがたまにあります。)
アルバムにデザインされたステッカー風のオブジェクトには、「Ra*bits は 宇宙空間 outerspace へ行く」とあります。「Ra*bits」はどこまでも飛んでいける、というような未来への希望を表現しているのかもしれません。
なので、ラビッツの空(宙)の旅は、飛行機とスペースシャトルの中間みたいな、飛行機に見せかけて、実は宇宙にも行けちゃうよ!という感じかなと思ってます。そう解釈した方が、なんだか楽しい。特に、今回の衣装の「星」のデザインは光くんが考えたそうですが(アプリ内キャンペーン「MC9」)、光くんのソロ曲には「宇宙」というワードが入ってますよね。たぶん、他のメンバーは、お空を飛びたいな〜くらいのことを言っていたのに、光くんが、それじゃ物足りないんだぜ!宇宙にも俺たちならいけるんだぜ!とか言い出して、みんなをアウタースペースまで引っ張っていってしまうような、そんなイメージが浮かびます。
「ヒカリスペクトル」MVのステージも、グラデーションに光っていて、どんどんと遠くへ、高く高くお空を飛んでいくうちに、景色の色が変化していく様子にも見えます。


アルバムシリーズ第一弾の「Crazy:B」は、おそらく自動車の旅でした。オープンカーで海沿いの道路を……的な新曲MVのイメージに合っていましたね。そんなわけでおそらく他のユニットは、船とか、電車とか、飛行船とか、気球とか……また別の仕方で旅をするのでしょう。それぞれのアイドルロードを、それぞれなりのやり方で旅してる、っていうイメージでしょうか。だから、ユニットによって経路が違う。
「Ra*bits」は新旧ユニット衣装や、そのほかのいろんな衣装のモチーフが、だいたいよくセーラーでマリンなので、海、海路、船とかとも相性がいい気もしますが、ウサギは飛び跳ねるので、やっぱり「空」(宙)は合っていまね。衣装も、背中には「羽根」がついています(そう、天使だから当然ですね)。
もちろん言うまでもなく、「Ra*bits」のセーラーなモチーフは、一昔前にヨーロッパで子供服としてセーラー襟が流行ったことが起源でしょうけれども。少年っぽさ、「良家の子女」感を出すのに役立っているものではあります。個人的にこういうのは好きですが、今回のアルバム衣装はあんまりセーラー感がないのことにあえて解釈を加えるなら、「Ra*bits」はちょっと成長して、少年とか「良家の子女」といった枠組みでのかわいさから変化しつつある、もうちょっと広い意味でのかわいさを表現しつつある、それが衣装に表れている、と考えてもいいかもしれません。
創くんの表情など
ジャケットイラストの創くん……本当にますますかわいいです。ここ最近の創くんイラストで最高傑作かもしれない。そう、ウインクが得意ですよね。普段から自然としてそうです。創くんって、ちょっとまぶた重めの平行二重なのかなと思うのですが(前から思ってるけど、こういう目ってなかなか現実ではないし、特に東アジア系で天然ではなかなか見られない気がする。眠たそうな重めのまぶたって、一重か奥二重になりそうです。創くんは多分、ぱっちり平行二重ですよね。いいな)、目を閉じやすいのだろうか、などと考えてしまいます。
あと創くんの広げた指が綺麗。いつも思うけど。細くて長い。美しいです。
なずな、光
ちなみに、なずなくんの表情も絶妙ですよね……。なんだか、一瞬の差で写真の撮影の失敗になりそうな、そういうギリギリの、本当に自然な、動きのある瞬間を捉えた!っていう感じの表情ですよね。
多分スタジオでファンで風を吹かしながら、ジャンプして、その瞬間を撮影したやつだと思います(イラストですけど、設定的には。みんなで何回もジャンプして撮ったよね〜とか、リアルアイドルだったらフリーペーパーとかで?話してそうです)。

なずなくんは両足ジャンプして、一番がんばってジャンプしてますよね。思いっきりジャンプするんだな?よ〜し!とか言って、張り切ってそうです(かわいい)。それで、ちょっとお口をギュッと閉じた、がんばってジャンプしている瞬間が撮れたのかも。そういうのも全て想像してかわいいです。
(あとは、今回のソロ曲のテーマとか、少し前の「フィーチャー2」のテーマもそうでしたけど、元気な姿を見せる、飛び跳ねる Hopping …… というのがなずなくんのテーマになってきているようなので、アルバムジャケットの全力ジャンプは、それも反映されていると見ることもできるかもしれません。今回のアルバム衣装の「羽根」を提案したのも、なずなくんだったそうですし。)
あと細かいマニアック?なところですが、なずなくん、その全力ジャンプで力の入った時に、ちょっと筋が入ったしっかりした腕が撮影された感じがしますね。ダンスも得意なイメージがありますし、ちゃんと筋肉が結構ついてそうだと思います。
それと、ジャンプの直後に光くんがちょっとなずなくんの方に寄って行ってしまってますね。こういうとき、に〜ちゃんに負けないくらい、思いっきり楽しんでジャンプしてしまいそうな光くん。ちょっと、おっとっと、ってなってそうで、この撮影されたすぐ直後の瞬間のみんなの雰囲気を想像するのも楽しいです。
友也、創
そして創くんは、これ、ほとんどジャンプしてないですね。ちょっとワンテンポ遅れちゃったのかもしれません。それも創くんらしくてかわいいです(かわいいしか言ってませんね)。
でもむしろ、友也くんにぶつかったらとか、そんなこと考えてしまったのかもしれないです。優しいですからね。

この体勢だと、友也くんが左の腕を後ろに伸ばしていて、その腕と肩のあたりに、創くんは頭をつけるというか、ちょっとのせているような感じの状態ですよね。
この前のパラレルワールドのカードイラスト(友也くん星5才能開花前、3人でうたた寝しているイラスト)でも思ったのですが、創くんはやっぱり友也くんにスッと、自然と寄り添っちゃう感じがあるんだな、と。

なんていうか、もう本能的な、猫とかウサギとかが自然と安心する人のところにスッと来ていつの間にかくっついちゃってるみたいな。なんか安心する、無意識に……みたいな感じで、いつの間にか友也くんにくっつきがちになってそうな気がします。創くん。
よく見ると、ジャケットイラストでの二人の太ももと膝の形で、ハートマークみたいになっています。偶然かもしれませんが。仲良しです。
……などとこんな感じで、このアルバムジャケットイラストだけでも延々と楽しめてしまいます(味のなくならないガムみたいな)。
アルバム『TRIP』衣装
兎の耳、尻尾、羽根、一番星
「Ra*bits」は意外とこんなわかりやすくうさ耳をつける衣装って、実はそんなにない気がします。『!!』ではブラックバニーとかぐらいでしょうか。
うさ耳といい、もこもこ感といい、前作の1st アルバムでの衣装と違って、よりメルヘンな方向が強まったという気がします。すでに少し言及しましたが、セーラーカラーが想起させる「少年」とか「良家の子女」的なイメージから少し成長して、ややそこから脱しつつあるのかもしれません。「両家の子女」風も大好きですが、そんな例えば大きなお屋敷で大事に育てられているようなイメージではなくなってきているのかな、と。
でもかといっていきなり現実の世界の荒波で苦労している男の子みたいな方向も、なんだか違う。そういうわけで、メルヘンな世界の方へ飛び出していくのが正解かな、という気がします。

「兎の耳」を考えたのは創くんだということでしたね。今回の衣装はみんなで考えた、って言っていました(MC9)。
創くんが「耳」なのはなんでだろう?と考えていたのですが、ぼくたちRa*bitsだから、やっぱりウサギらしく、お耳をつけるのはどうですか、などと一番最初に提案したのかもしれません。それいいな、ということになって、そこから話し合いが進んで、いろいろみんなも提案していった(尻尾、星、羽根)、という流れがなんとなく想像できる(じゃあ尻尾も?とか友也くんが言い、おれは羽根があってもいいと思うんだ、オレは一番星を取り入れたいんだぜ、って)。
でも、あえて意味を読み込むなら、ひとの話をよく聞いて、寄り添う、という創くんらしさという意味で、「Ra*bits」の「耳」は、やっぱり創くんなのかもしれません。「紫之は聞き上手だから」って佐賀美先生も言っていましたよね。「尻尾」を提案した友也くんは、方向を決めたりする舵取り役ということかも。「一番星」はなんと言っても光くん。スーパースターになる!って言って、遠い目指す場所(ゴール)へとメンバーをぐいぐい引っ張っていきそうです。
そして、に〜ちゃんが「羽根」。確かに、に〜ちゃんがアイドルのことを教えてくれて、彼らに翼をくれたんですよね。こんなふうに考えると深みがあります。もちろん想像の域を出ませんが。
うで
フードのついたケープみたいなものかと思いきや、ノースリーブなので、ベストのような、暖かいようでそうでもなさそうな、あんまり現実的ではないお洋服で、これもメルヘンです。
腕が。肩が。結構出てますよね。「ニューイヤーライズ」でも、けっこう腕出すな〜と思ってましたが、一応「ケープ」もありました。

「Ra*bits」や創くんの衣装ということでは、肩を出すのはそんなになかったと思います。『!!』になって、ユニット衣装もあんまり露出が減って、これからのRa*bitsは肌を減らしていく方向なのかな、と思っていました。
と言っても肩の出し方(?)が絶妙で、腕を動かすと出るという、ちょうど良い出方(?)ですね。ちらちらと肩が出たり隠れたりして、まったくもうです。
MV衣装を見ていると(3DCGだから個人差があるのかどうか知りませんが、そういうメタ事情はあえて無視して)、やっぱり、なんか腕がしっかりしてはるな、と。もこもこの腕カバー(?)から出ている、ちゃんとしたシッカリした腕。良いです。
多分リアルなら、ライブ映像なんかを見ていると微妙に腕を動かしたときの筋とかの動きが見られると思う。そういうのが、なんとも絶妙に良かったりする。かなり細かいことですが。
おへそ
お腹も出ていますが、その出ている幅の細さも絶妙です。おへそが見える衣装も、『!!』以降ではおそらく創くん初めてではないかな、と思うのですが。貴重だ。(シティライダーの星3イラストではありましたが。あと、MV衣装の方では、いろいろの理由から?しっかりしまわれています……)
なんとなく創くんは、もう大きくなったし(?)、おへそを封印したのかな、と思ってました。それはそれで全然いいんですが、創くんのお腹がどんな感じなのかは、ちょっと知りたかったので(変態なので)。ムキムキ腹筋はちょっと、と思いますが、しかし割としっかりしてきたかな、くらいが理想だなあと勝手に妄想しておりました。まあ結局、CGとかイラストからはよくわからないんですけど。
(創くんのお腹が気になり出したのは、アニメのときのイラストがけっこうぽっこり丸いお腹で、幼児体型な感じが強調されているな、と思ったところからです。ちょっとやりすぎなくらい丸いなとも思いつつ、でも運動も苦手で、入学したばかりの創くんだとすれば、むしろあのような感じが適切だなとその時は思いました。それ以来、創くんのお腹はその後どうなっているの?丸いの?というのを何となく気にしていました。本当に変態のようですみません。しかも気にしている割に、結局どっちだとしてもかわいいよなあ、としか思いません。すみません。)
CDのボックス、ケース、等(物理的な手触り)
「CD」は、リアルな物体としてそこにあることが大きな意味を持ちます。手に取って、開いて、触り心地や光の反射とか、さらには工場から出荷されたての紙とかプラスチック?の匂いまでも含めて、体験だと思います。
特典のポスターなど
確実に手に入れるために、私はアニメイトの通販で予約していました。正直、あんまり限定特典とかにこだわりが少ない方ですが、とにかく一番いいやつで!ということで、有償特典付きにしました(かわいいバッジが付いてた)。なんとなく旅行とか特別なところで食事をするときなどにメニューで迷ったら、せっかくだし一番いいやつで!みたいな感じです。
段ボールの箱を開けた段階で、もう、わあ〜〜!!という特別な気持ちになりました。なんかかわいいのがいっぱい入ってる!って。

A3ポスターらしきもの。先着特典でしたっけ。クリア素材で、美しいです。いや本当に美しいな……。やっぱりこのアルバムのジャケットイラストは本当に素晴らしいと思うのですが、特にこのビジュアルを一番大きなサイズで見たのがこのポスターかもしれません。デジタルデバイスでは、もう予約の画面やゲームの画面などで何回も見たイラストですが、一番大きなサイズで間近に見たのは、このポスターが初めてだと思う。デバイス越しではなく、直接に目で見られるのもいいですし。やっぱり予約しといてよかったと思いました。
そこから、このA3ポスターをきちんと飾ろうと思って、すでに持っている額縁を探したのですが、やはりここはスカイブルーの額縁が絶対いいと思って、ネットや画材屋さんであれこれ探し始めてしまいました(けっこう時間を使った)。

結局、ちょっと特殊な、奥行きのある箱みたいな形のスカイブルーの額縁に飾ることにしました。アルバムのトランクケースの箱っぽさを意識したのと、壁に掛けたとき、そこだけが切り取られた空間のように見えて、なんとなくこのアルバムの世界観みたいなものが出るかな、と思ったので。
ボックス、紙の材質
それからかなり豪華で凝りに凝ったジャケット……というか、ケースとか諸々の付属品とか歌詞カードなどを堪能しました。
トランクケース風になっていて、ちゃんと取手が持てるんですね。でも紙だから重量とか耐久性には気をつけてね、って書いてありました。行ってきま〜すとか言って、ここだけ持ってぶらぶらと出かけたりしたらダメですね(もげます)。

パスポートとか、チケット風の歌詞カードも本当に凝ってます。使っている紙の材質、質感までそれっぽくなっている。このアルバムは、手触りとか、触覚でも楽しめるんですね。とあるアーティストさんのアルバムで、やはりこういう、ほとんど音楽に関係ないような細かいアイテムがゴロゴロ入ったかなり豪華なものを以前買ったことがありましたが、それを思い出しました。音楽はデータとしてはデジタルで配信されているからこそ、「ディスク」を買ってきて、箱を開けて、っていう楽しみは、むしろ増えたのかもしれないですね。聴覚だけじゃなくて、視覚、触覚、さらには嗅覚も含めて、音楽作品を楽しめる。
特に、2次元アイドルの、スマホアプリゲームの音楽なのに。最もデジタルで、最も形がなさそうなものなのに。でもむしろだからこそ、リアルの質感や、ざらざらした手触りのある物体として、この作品を味わう機会が持てるのがとても嬉しいですね。ちょっと大袈裟に言えば、一緒に生きている、って感じられます。寄り添うアイドルという創くん(たち)のテーマともつながりますね。
歌詞カード
次に、音楽を聴く前に、まず歌詞カードだけをじっくり読みました。私はリアルのCDを買ってきたらまずこういう楽しみ方をします。人によると思いますが。「ヒカリスペクトル」やソロ曲は初めて目にしますし。
それだけでもう……ああ、なんだか、本当に感動して涙が出そうです(歌詞カード汚さないようにしないと)。特にソロ曲の歌詞ですね。創くんたちのことを、本当に深いところまで考えている歌詞なんだな、って思えました。本当に素晴らしい歌詞だと思いました。歌を聴いてないのに、すでに感動してしまった(ゲームのキャンペーンをやっているので、ちょっとだけ聴いてますが)。
ディスク、ケースの路線図
CDのディスク本体も、大事に大事に、奥にしまわれています。CDのケースには、路線図みたいに曲順が書いてありました。私は「名古屋」の地下鉄を思い出しました。

数ヶ月前、私はやっぱり、あのJR東海さんのコラボ(「新幹線で行く!『好き』を巡ろう JR東海×ENSEMBLE SQUARE イチオシTRIP!!」)を実践してきたのですが、名古屋はあんまり慣れていないので、駅で何度も路線図を見て、商店街とか、ウサギの神社とか、あと、例の「山」に登頂しにいったりとか……。なんだかリアルの自分の思い出にもなったし、このアルバムの路線図を見て、思い出すことができました。まさにアルバム、旅の思い出ですね。みんなと一緒に旅行に出かけたかのような、それを今思い出しているかのような、そんな気分になりました(迷ったけどやっぱりあれ実践して良かった)。
「TRIP」というテーマは、どういう意味なのかよくわかっていない部分もあるのですが、私にとっては、あの旅の思い出とも重なりますし、もちろん、「Ra*bits」のこれまでの軌跡を表現したものにも思えます。
そういえば(同人誌にも書きましたが)、Ra*bitsは「電車」に乗ってましたよね。「出発新GO!」とか、「ハッピースプリング」でも電車に乗っていた。みんなでお揃いの制服(スーツは制服)で、電車に乗って出かける。CDジャケットの路線図は、そういう「Ra*bits」電車の軌跡にも見えます。
さらにそこに名古屋の地下鉄が重なるという、なんだか不思議な感覚を得ました。そういえば、アプリ内キャンペーンの「アルバムスタンプラリーRa*bits」も、名古屋のコラボでのスタンプラリーを思い出させました。QRコードを読み込んでいくんですよね。──人通りの多い駅の売店の横とかに突然、あんスタのポスターが設置してあるのが不思議な光景だった思い出です。


さらにCDのケースを取り出すと、またその後ろにメンバーのカードが入っている。かわいい。──ちなみにその下の台座は、本当にただの台座でした。何か隠されていたり、裏側にイラストがあったり、そういうのはありません。ボックスの全体に、トランクっぽい厚みを出すためにも必要なものなのでしょう。

アルバムの構成、インスト曲、ユニット曲、曲順など
全体、1stアルバムとの比較
ユニット曲は、「ヒカリスペクトル」を除いて(および「パラレルメイズ」のフルバージョン)、もちろん全て既知のものです。
けれども、こうやってアルバムの流れの中で聞くとまた違う気がします。本当に、これまでの旅の思い出という感じがします。
また、改めてじっくりと1stアルバムと比較して聴きたいな、という思いも強まりました。2ndが出て比較対象ができたので、1stアルバムがどういうものだったのかを改めて考える手掛かりにもなると思います。
ひとまずすぐに言えることは、1stアルバムでは、ぼくたちのストーリーが始まるよ(「主人公」の「ストーリー」)、ぼくたちの世界にようこそ(「Joyful x Box*」、「Love Ra*bits Party!!」)、応援してね、というのがメインで、2ndは、みんなの応援でぼくたちはここまで成長してきたね、と振り返ったり、さらにこれからも一緒に成長していこうね、と聴き手を応援したりもするようになっています。「ずっとパワーアップしてるでしょう?」(なずな、MC7)、「あなたを応援するために、ぼくたちもがんばり続けます……♪」(創、MC8)
「うさぎの森の音楽会」の位置付け
そういう流れの中で位置付けると、やっぱり「うさぎの森の音楽会」*2は重要だなあと思いました。特にこのアルバムの中でもそれを感じました。Ra*bitsの変化や成長がよく表れていると思います。
というのも、この曲は一見すると、従来の「Ra*bits」らしい、ぼくたちののかわいくて楽しい世界へご招待!(「Love Ra*bits Party!!」、「Joyful x Box*」みたいな)というような、従来的「Ra*bits」の様式を踏襲しているように思われます。1stアルバムに典型的な雰囲気で、ともすれば一緒に入っていても違和感がなさそうですらある。
けれども曲を聴いていくうちに徐々に、あれ?なんか違う……と気がつきます。聴き手のことをいたわったり、励まそうとして、「応援する側」になってきている。ここに彼らの成長を感じて、ちょっとびっくりするのです。
規範と逸脱。伝統と革新。従来的な「Ra*bits」のコードと、そこからの逸脱とが巧妙に組み合わさっていて、その結果、「Ra*bits」の変化や成長がじわじわ、ど〜んと感じられるようになっていると思うのです。
そこから「ハレノヒSugar Wave」に至る道筋があって、みんな(聴き手)を「応援する側」に転換していく。……なんか樹形図みたいなので示したくなりますね。「Love Ra*bits Party!!」から「うさぎの森の音楽会」へ。そこから「ハレノヒ」へ。また、「うさぎの森」と同じCDの「FALLIN’ LOVE=IT’S……」はそこから枝分かれした別の系統だけど関連していて……って(「Love Ra*bits Party!!」での「背伸び」が、だんだん板についてきて、「ハレノヒ」ではその分の成長に繋がっていたり。その間には「うさぎの森」とか「FALLIN’……」があったり)。「Ra*bits」ソングの進化の樹形図、ないし系統樹。また、そうやっていろんな方向へ広がって育っていく有様というのが、言い換えれば「Ra*bits」の「スペクトル」なのかもしれません(後述)。
インスト曲
インスト曲もいいですね。オルゴール風。オルゴールって、大事なものをしまえる宝箱みたいな作りになっていることが多いですが、そこに思い出の品がこまごま、ちまちまっとしまわれているような、そんなイメージが浮かびます。今回のCDも、ケースがトランクケースのような、「箱」のような作りになっているので、箱を開くとRa*bitsの思い出と共に、オルゴールが流れ出す……というような体験にも思えます。
アルバムって、その名の通り、思い出のアルバムみたいですよね。そういえば、に〜ちゃんのお誕生日に創くんが確かアルバムを作ってプレゼントしていたと思います。そういうことって、あのお誕生日の時に限らずときどきしているのかな、と想像したりします(かわいいです)。仲良しのRa*bitsならしてそうです。そんな彼らの手作りのアルバムを見ているような感覚にもなりました。
ユニット曲の流れを締めくくる、2つめのインスト曲「*Happy Closing*」は、やはり1曲目と同じ「ヒカリスペクトル」なのかなと思ったら、「ハレノヒSugar Wave」でした。「アラナミに飛び込もう」の部分が、原曲にはない形で、2回繰り返されています。
これから前に進んでいく、という印象を残しながら、クロージングする、という感じでしょうか。イベント時系列的には「パラレルメイズ」が最後に当たるのですが、正直なところ「ハレノヒ」の方が、私は「Ra*bits」のこの1年間の締めくくりとしてはしっくりくると感じていましたので、その意味でもこの曲順は良かったと思います(もちろん曲順そのものは、メンバーの順番通りにそれぞれのセンター曲を配置しているだけかもしれませんが)。
新曲「ヒカリスペクトル」
*3
歌声など
本当にメロディも歌声も素晴らしい曲だと思いました。とにかくとっても美しい歌声が楽しめます。こういうしっとりめの曲調のおかげで、伸びやかなメンバーのコーラスがじっくりと聞けます。
この歌も、ソロ曲でもそうですが、今回のアルバムではけっこう皆さんファルセットっぽい歌い方をされていますね。「Ra*bits」の曲でこういう歌い方って、これまでなかったような気がします(記憶の限り)。「Eden」とかのイメージです。少し大人っぽい印象があるかもしれない。こういうところからも、彼らの成長を印象づけてくれるようです。
光学的な比喩
歌詞に関しては、全体的にふんわりとしていて素敵なのですが、ちょっとだけ微妙にも感じられました。特に、ゲーム内のライブ・MVでは使われていない部分だと思いますが、「ゴミ箱行き」とか、あんまりわざわざ「Ra*bits」の歌で出てこなくても良いような気もします。もちろん、強い言葉を使って、意志とか決意とかを表す意図があるのかもしれませんが。今回の歌詞は、少し従来的な「Ra*bits」のかわいらしさを落として、その代わりに意味の方を追求しているような印象を受けました(けれども、この両者は必ずしも二者択一ではなく、「うさぎの森の音楽会」や「ハレノヒ」などのように両立することは可能だと思います)。
「ヒカリスペクトル」って、そもそもこの言葉が何なのだろう?と思うのですが、先ほど樹形図で「Ra*bits」の歌の進化を示したくなるなどと言ったように、いろんな方向へと「Ra*bits」の可能性の輝きが広がっていく有様というのが、たぶん「スペクトル」なのかな、と私は思いました。
分光スペクトル。つまり、光[ひかり]はプリズム装置を通すことで、「分散」します。紫色、青、緑、黄色、赤、と、波長によって方向が変わる。そこで「虹」ができる。
虹を何色と数えるかは文化で違うと言いますが、メンバーカラーも4色にバラバラだということを考えると、「Ra*bits」というプリズム装置から「分散」していった各メンバーのそれぞれの色の光が輝いて、虹をかけているような、そんなイメージの曲かなと思います。「空に浮かぶ」という歌詞もありますね。今回のアルバムのテーマも「空」(ないし「宙」)なので、そういう虹のかかった綺麗な空の景色を旅して、「灯りの行方」を追いかけていく。そういうイメージになぞらえて、「Ra*bits」のアイドルロードの旅路(TRIP)を表現しているのかもしれません。
だから、「スペクトル」というのは、個性=「凸凹」が噛み合って、素敵な「景色」を見せてくれる(Branco「白雪たち」での桃李くんの言葉)──っていう、「ユニット」概念を表現したものだと言えます。その意味では、「Ra*bits」に限らず、アイドル一般のテーマ曲として通用する気もする。
ただ、個人的には、空にかかった虹を追いかけて……というイメージから真っ先に思い出すのは、やっぱり創くんの『!』星5カード「虹色のプリズム」です(後述)。「ヒカリスペクトル」って、この「虹色のプリズム」を言い換えたような言葉にすら感じる。あのカードイラストやストーリーはとてもとても大好きなので、そういう意味でもなんだか嬉しいですね。
「灯りの行方」
「灯りの行方」という言い方も気になりますが、メンバーがそれぞれ、割と独自の方向性を示しているのが最近の「Ra*bits」だとも言える。よくそういう言及のされ方もしますよね。「ちがう道」でも「おんなじ気持ち」というお話もありました。
プリズムは、分光器とも言います。光[ひかり]は分光器を通って、スペクトルに広がり、「分散」する。「Ra*bits」という分光器、プリズム装置があって、そこに、みんなの光[ひかり]が入って、いろんな方向へ可能性が広がっていく。その「灯りの行方」のうち、どれを追いかけるかの選択はぼくたちでやるよ、と言って、それを追いかけていく。どの分光された光が正解か、答え合わせだって楽しもうぜ、って。
だから「灯りの行方」というのは、「Ra*bits」がこれからどう進むのか。それも、メンバーによって、ちょっと違うかもしれない。「分散」していくかもしれない。でもそれでも進もうよ、ということでしょうか。その方が虹は綺麗だと。
実際、このアルバムでも、ユニット曲が各メンバーのセンター曲順に並び、さらにそのあとソロ曲が並びますが、けっこう毛色が違いますよね。もちろん、はっきり違うと思うのはやっぱり「FALLIN' LOVE=IT'S WONDERLAND」でしょう。イントロから明らかに異色。光くんセンター曲で、これはやっぱりなんと言っても光くんらしい、かっこよさのある曲です。光くんソロ曲もはっきり特色がありましたね(後述)。そういうそれぞれの特色が虹のスペクトルのように輝いているアルバムだと思います。
「反対側」、「逆立ち」
「反対側」「逆立ち」っていうのは、この曲の光学的比喩の流れからすれば、レンズ(凸レンズ)の「倒立」した像みたいなことでしょうか。ビー玉とかを覗いて、反対向きに世界が映っている!みたいな体験を子供時代にしたことのある人もいるかもしれません。そういう意味では、少しノスタルジックな、昔を思い出すような雰囲気もありますね。これは「泣かないで」という歌詞もあわさって、「講堂」の過去の創くんを、反対側の観客席で見る「夢」の中の創くんを思い起こさせます(「出発新GO!」ストーリーより)。綺麗なビー玉越しにのぞいてみれば、昔のあの頃のつらかった自分たちの姿も、また輝く光のプリズムの一つになる。いま、未来へと進む糧になる。そんな意味でしょうか。
「嫌なことを嫌だって言っても」
いろんな可能性が「Ra*bits」というプリズム装置から見えてくる。その中で、好きなものを選ばせてもらうよ、というような意味かなと思います。こちらで決める、嫌なら嫌って言うしね、って。
嫌なら嫌って言う、受け取るかはこちらで決める。これは私も活用させてもらおうかなと思いました。推し活とか、オタクって、何でもかんでも受け止めないといけないみたいな変な義務感が出てきて、楽しいはずのものがうまく楽しめない場合もあるかもしれません。まあ、好きなようにしたらいいんですが、やっぱり自分の人生が充実するかどうか、楽しいかどうか、これが結局は一番の基準だと思います。
「綺麗になる」
「どんどんキミは綺麗になる」。確かに「綺麗」だなっていうのが、私が最近特に、創くんたちについて思っていることです。「想い降り積もってく」という雪のような比喩は、どう繋がるのかなとは思いますが。
ただ「想い」と「綺麗」というのが結び付けられているのは良いなと思いました。私も創くんの想いや内面的なものが彼の美しさであると、最近特に思っています。
また、大きくなったらかわいくなくなるんじゃないか、みたいな懸念を、『!』時代などに彼らは時々していましたが、むしろ逆だ、という話ですよね。ここで歌っていることは。歴史を重ねて「降り積も」ることによって、むしろ「綺麗」になる。確かに、かわいいというより、綺麗な人っていますよね。綺麗な方はずっと綺麗です。内面から来る綺麗さというのはあると思います。
「多少の痛みは ほら」
MVの創くんの振り付けでは、この「多少の痛みは ほら」のところが本当にかわいくて、手のひらを閉じたり開いたりする(グー・パーするような)動作がとってもかわいいです。しかもそれをしながらウインクしてくれるんです! もこもこのアームカバーから伸びている指が細くてとっても綺麗ですし。いわゆる萌え袖の状態で、指の美しさが強調されますね。



このグー・パーの動作の意味はよくわかりませんが、あれはなんだろう?って思わせるところなどから、なんとなくおまじないっぽい感じなのかな、と想像しました。痛いの飛んでけ〜、みたいな、「多少の痛みは ほら」って。確かに、創くんのおまじないは効きそうです。特にこの歌詞の内容からしても、創くんは自分が過去に「痛み」を乗り越えたことがあったから、みんなも大丈夫だよ、っておまじないをかけるように言ってくれているようにも受け取れます。
「いこう」
創くん「オリジナルSPP」は、「いこう」という歌詞に合わせて、空を指差して終わりますね。旅の始まり、出発ということなのかもしれません。アルバムの1曲目であり、「単独ライブ」(アプリ内「アルバムスタンプラリーRa*bits」)でも1曲目ですね。

また続けて曲の最後、MVでメンバーが「いこう」と言いながら手を差し出します。Ra*bitsの旅路(TRIP)にご招待、さあ一緒に行きましょう、と言っている。「灯りの行方」を一緒に追いかけようよ、見に行こうよ、って誘いかけてくれているようです。やっぱり、一緒に歩もう!と言ってくれる「寄り添う」アイドル像が反映されていますね。ファンは「Ra*bits」の成長を傍観して追いかけるだけではなくて、一緒に成長する、一緒に(自分の道を)がんばる。そういうファンとの関係を作ろうとしているのだと思います(後述)。

ソロ曲
良い曲ばかりですし、1stのソロからの変化やその背景にある物語を考えたりすると、さらにいろいろと味わうことができると思います。また、歌い方なども高度な?というか、難しそうな感じが多いですよね。Ra*bitsの歌が上達している、ということも反映されているのでしょう。
真白友也 Solo「Centre of the theatre」
友也くんのソロ曲、いい!!ってなりました。歌い出しの、ぽつりぽつりと独白するような歌い方が本当によくて、鳥肌が立ちました。友也くんの少しだけかすれたような声が、この歌い方にとても合ってる。なんだか、有名アーティストのアルバム収録曲で、名曲とされている曲、といった感じの曲です。
前回の1stのソロ曲は、「たはは……」っていう友也くんのあのかわいいボイスを思い起こさせるような曲で、まだまだこれから、スタートラインだ、っていうような内容でした。今回は、友也くんがお芝居を頑張っていて、それをテーマにしながら友也くんの内面に迫るような歌だと思います。友也くんの歌声が、そんな内省的な雰囲気にとってもよく合っていました。
歌詞の「君」は、ファンとか、あとは原作の設定を考えたらプロデューサー(転校生)でしょうかね。ただ、少し広げて先輩とか、他の人でも良いかもしれません。私の場合だと、創くんだと思ってもまあいいのかな……という感じもいたします。お芝居を見に行ったりしているようだし、大親友だし。
仁兎なずな Solo「Hopping on the music notes!」
「コーレスがいっぱいの楽しい曲です」(なずな、MC6)。
元気さ、飛び跳ねる、というテーマ。「フィーチャー2」のテーマもそんな感じでしたね。
あとは、翼。声に翼が生えていて、歌に乗せて思いがいろんなところに届くというような内容でしょうか。友也・創の中学生時代のお話など、歌声は思いがけずいろんなところに影響を与える。そういうことがモチーフなのかなと思います。今回のアルバムの衣装は、「羽根」をに〜ちゃんが考えたとのことですし。
あと、このなずなくんソロ曲にも「君」が出てきます。このあたりもあれこれ考えると面白そうなところです。
それにしても、声や歌い方が、う〜んやっぱり……かわいいです。に〜ちゃん。一生懸命に歌っている!という感じが絶妙に出ている歌い方です。本当に、リアルでのアイドルの歌みたい。ちょっと声高めのボーイズグループの曲っていう感じがします。なんか、すごく応援したくなる。
天満光 Solo「SUPER SPACE STAR☆」
光くんの曲は、とっっても!かっこいいですね。曲調もコズミックな?感じです。光くんは本当に光(ひかり)だなあ……ひたすら輝いてる。こんな太陽みたいなエネルギーの人は、本当に元気をくれます。メンバーもそう思ってそう。
曲調や音の感じもすごくおしゃれでハイクオリティです。なんか光くんだけ海外でレコーディングしてきた!的な感じすらある。1stアルバムのソロ曲と比べても、雰囲気の変化が大きくて、成長が著しいですよね。歌い方も大人っぽいところがあって、「Oh yeah」のところとかかなり渋いです。光くんの歌でもファルセットっぽいのがありますね。
でも歌詞を見ると、かっこいい部分もあるけれど、1stのソロの系統を引くような、無邪気さ、元気さもかなり出ていて、そのギャップも良いですよね。
こんなにかっこいい曲なのに、エピソードトーク的なときには、ロサンゼルスではいっぱいおいしいパンを食べたんだぜ〜!!などと話してくれそうです(かわいい。完全に勝手に海外レコーディング設定になってますが。穴の空いたモチモチのパン!!ベーグルのこと?とか。ロサンゼルスのパン屋のイメージ)。
紫之創 Solo「ボクスケッチ」
*4この曲に関しては、もう本当に、素晴らしい、良かった、というより他に感想がない……。というのも、いまの創くんのことを本当にしっくりと表現している内容で、あまりにもピタッ!とハマっているように思うので、もはや私などがそこに加えて言うようなことが見当たらないのです。
逆に、もしこの歌の感想をちゃんと書こうと思ったら、いまの(いままでの)創くんのことをすべてちゃんと語ったり考えることが必要になってしまうでしょう。それはすぐにはできません(というより、一応私なりに、ついこの前、本(同人誌)につらつらと書いたことでもある)。
「ぼくもこの歌が大好きです」(MC9)と、創くんが自分で言っていました。本当にこのことに尽きると思います。いまの創くんそのものを表しているのです。

それでもあえて、ポツポツと思ったことを断片的に記しておきます。歌詞のことばかりになってしまいますが、もちろん音楽も、歌声も、とっても素敵でした。こういうちょっとゆっくりしっとりしたテンポの曲は、すごく創くんに合っています。
全体を通して、なんとなく「フィーチャー2」の才能開花前イラストが思い浮かびました。ひだまりの庭園、自分の好きな場所で、穏やかな時間を過ごしている創くんの姿。癒されている創くんに癒されます。

1stソロ曲との比較 お茶と絵
1stアルバムのソロ曲「Happy Coming*ティータイム」は大好きですし、かわいくて大興奮ものでした。けれども、創くんが一方的におもてなしばかりするような、他の人にばかり配慮するような内容にも見えることは、少し気になっていました。そういう性質は彼の美徳であると同時に、彼を悩ませてしまう原因にもなっていたので。創くんが、おもてなしが好きなんです、と言うとき、それは素敵なことだけど、創くん自身は大丈夫なの?と思ってしまうところがありました。
だから今度のソロ曲では、もう少し創くんが一人の人間として生きていく上での内面を掘り下げてくれたらいいなと期待していたので、全くその期待通りの歌詞でした。
今回のソロ曲では、まず創くんが主人公の自分のストーリーを歌っています。そしてさらにその上で、同じようにあなたも一緒に歩いて行こうね、と言ってくれる。こういう形で、応援してくれるんです。
1stはお茶の趣味で、2ndは絵の趣味をテーマにしています。創くんはやはり紅茶部での活動を中心にしたお茶の趣味が有名ですし、専用衣装のテーマにもなっています。お茶は学院に入る前から好きだったそうですから、元々の創くんらしさを反映しているものと言えます。
けれども、絵を描くのも昔から好きだったんですよね。スケッチブックに絵を描くというのは彼の昔からの趣味で、かつては誰かに見せるということもなく、ただ描いていたそうです。それは自分のために描いていた。自分のことを考える、自分らしく生きる、というテーマを歌うには、やっぱりこの「絵」(スケッチ、ドローイング)のモチーフが合っているのだと思います。
物語を紡ぐ、絵(世界)を描く
「ココロの大事な場所」、「小さな頃の」、「自分らしい道」──こういう言葉が散りばめられていて、過去から現在、そして未来へと続く「紫之創の物語」を、彼が自分の手で描いていくことを歌っているものだと思います。
『!』で、虹を見て感動している創くんのイラストがありますが(星5「虹色のプリズム」才能開花後)、子供の頃はもっと「やんちゃ」なところもあって、無邪気だったことを話してくれていました。そういう創くんの自由な姿というのが、絵を描くという昔からの趣味を軸に、だんだんと取り戻されていく。そういう姿が思い浮かびます。

「描いた世界」とありますが、結局、自分はどんな人生を送りたいのか? を考えるということは、どんな世界に生きていたいのか? を考えることと切り離せない、というより同じことになります。「世界」というとわかりにくいかもしれませんが、「環境」 Umwelt (環世界)ですね。未来の自分をイメージするということは、同時に、どんな環境で、どんなふうに過ごしているか、をイメージすることだと思います。
「今」という材料、能動的に生きる
「今の自分で塗り足しながら」というのも素敵だなと思いました。「絵の具」は、「出会った今日のなかに」探すんですよね。たしかに「未来」の材料は「今日」からとってくるしかない。
ただし、自分で能動的に見つけるし、探すし、選ぶんです。ただ与えられた「今日」を受け入れて、受動的に流されていくのではない。選ぶし、見つける。出会ったいろんなものの中から。そして、選び出して、見つけ出した材料で、未来を、この物語の続きを、自分の手で描いていく。
聴き手に対しても
創くんは今回、基本的に自分のことを歌っていると思うのですが、ある箇所で「この歌声にのせて 素敵な色を届けますね」と歌っています。歌いながら「この歌声」と自己言及するところも面白いのですが(つまりここに創くんの「ぜんぶ」が現れているということだと思うのですが)、この箇所があることで、この歌全体が、創くん自身の歌であると同時に、聴いている私たちの歌でもあることに気付かされます。創くんのがんばる姿が、私たち(聴き手)が歩む道のための「絵の具」=エネルギーや、手がかりにもなるのです。
「〜しましょう」という印象的に繰り返される語尾にも、創くんが自分のことを言っていると同時に、皆さんもそうしましょうと話しかけているようでもあって、ダブルのニュアンスがありますよね。
これはつまり、「ハレノヒ」でも表現されていた「寄り添う」アイドルですよね。創くんは、創くんらしい自分の道を歩む。その姿が、同時に、私たちが私たちらしい道を歩む時の心の支えになったり、手掛かりになったりする。そうやって、一緒に歩もう、と言ってくれる。
一緒に歩む、というのは、必ずしも、一緒の道を進む、ということではありません。お互いがそれぞれの道を進みながら、励まし合うという関係です。付和雷同はしないけど切磋琢磨はする、というような。
アイドルとファン(曲の聴き手)の関係は、こうしたものですよね。単純な話をいえば、ファンはアイドルになりたいわけじゃないですし。それぞれの自分の生活(ザッヘ、お仕事、ルーティン)を頑張る日々が、「推し事」を通じて結びつく。
というかその前に、たぶん「Ra*bits」もそういう関係になりつつあると思います。それぞれの活動が際立ってきている。「Ra*bits」は分光器・プリズムであって、メンバーのスペクトルが広がって輝いているんでしたよね。違う道、でも同じ気持ちなのです。
創くんがこれまでに経験してきた、ユニットや仲間の「寄り添う」関係が、次第にアイドルとファンとの関係にも応用されつつある。これが最近の創くんの考え方だと思います。
Special Disc(共通曲のRa*bitsバージョンなど)
いっぺんに味わったらもったいない気がして、ちびちび楽しんでいるうちに、一週間経ってもまだディスク2を聴けていません。何をやっているんでしょう。
まずジャケットとか、特典のポスターとか物理的なものを味わい、次に歌詞カードを読み、次にディスク1の前半(ユニット曲)を味わい、そのあとソロ曲を味わって、特に創くんのソロ曲はまた別でじっくり味わい……と、ここでもう一週間です。まだディスク2に入れていません。これから聴きます。
アプリ内キャンペーン
単独ライブ
アプリ内キャンペーンの「アルバムスタンプラリーRa*bits」(「単独ライブ」)ももったいない気がして、ちょっとずつ進めました。
たぶん「MC」は保存されて見返せますが、あの途中のスタンプラリーの動きみたいなのは取っておけないですものね。スタンプラリーをしながら、ぴょこっとメンバーのミニキャラが動くのがとってもかわいいので、つい大事に進めてしまいました。

ちなみに、「単独ライブ」の曲順は、アルバム順ではないところがちょっと面白いですね。光くん関連の曲(「FALLIN’LOVE=IT'S〜」、ソロ)が、ググッと前に持って来られている。最初の方に歌うと会場が盛り上がるからでしょうか。創くんの「おいで」で盛り上がるんだ、とかそういう話も出ていました(MC2)。
カードイラスト
このイラスト、みんなくっつきすぎだから、誰のカードにも誰かが写り込んでしまうのがかわいいですね。仲良しです。
友也くんと創くんなんか、もう絶対に別々のカードにはできない!というようなくっつき方です。かわいいです。

スカウト、SCR衣装
今迷ってるのはスカウトですね(「アルバム発売記念スカウトRa*bits」)。2枚も確定なんだからすごいスカウトなんですけど。なずなくんだけがなぜかすぐにマックス来てくれて、色違いの衣装(SCR)がすぐに手に入ってありがたかったんですけど(その後もなずなくん、すごい何枚も来ていると思う。アイテムに変換されてしまっています)。創くんだけがなぜだか全然、2枚目から来てくれなくて。どうしようかなと。もともと貯めていたダイヤと夏休みセットのBまで使い切ってこの状態です。Cに手を出すべきかどうか。

通常衣装で十分かわいいし、色違い(SCR)まで望むべきかどうか。正直、普段はあんまり、こういうところにこだわらないのですが。まあいいか、で終わるのですが。
ただ、今回の色違い衣装は、単に色を変えただけというより、Ra*bitsカラーの水色が前面に出ていて、すごく綺麗だなと思いました。空の旅をイメージしているので、色合いもマッチしていますし。ゴールドも星の色だからすごく綺麗に合っているんですよね。また、通常衣装に使われているビビッドなオレンジがなくなった分、ちょっと上品になった感じもします。に〜ちゃんの動くSCR姿を見ていて、いいなあ、と思いました。に〜ちゃんいいなあ、創くんにも着させてあげたいなあ、と。


とはいえ、もう何年も「あんスタ」を続けてきていながらなんなのですが、やっぱりデジタルデータに何万円もどんどん使うのって、どうしても抵抗があります(まあ、累計でなら分かりませんが……計算しませんが)。そしてこの抵抗感は、無理やり打ち消すのではなく、むしろ大事にしていい感覚なんじゃないかなと思う自分がいる。
でもやっぱり今回の色違い衣装は、特に良いと思うから迷います。もう少し悩みます。
もし現実のお洋服でこういう感じの色違いが出ていたら、散々迷ったあげく2色とも買ってそうだな、と思います。なんかいろいろ言い訳を考えて。
(おまけ)MV「FIST OF SOUL」
白うさぎvs黒うさぎ。
うちにはうさ耳衣装持ちキャラが藍良くんしかいなくて、藍良くんなら創くんが一番繋がりあるかなと。Brancoで先輩後輩として支え合った感じがあったし。というわけで、藍良くんの黒うさぎに合わせて、創くんも黒うさぎさんチームに。のこりはに〜ちゃん率いる白うさぎさんチーム。



ボギータイムの権利をもらったとか言っていたけど、いつの間にかずいぶんハードな内容になったな……というイメージ。はいしょうもないです、失礼しました……。
(このMVクオリティが高すぎて、別のゲームが始まったかと思うほどで、けっこう好きなもので……。なにげに新しい衣装が手に入ったら、1回はこれに入れて遊んでみているかも……。)